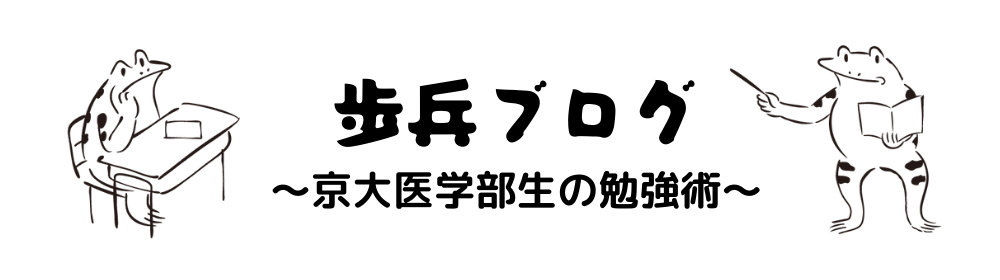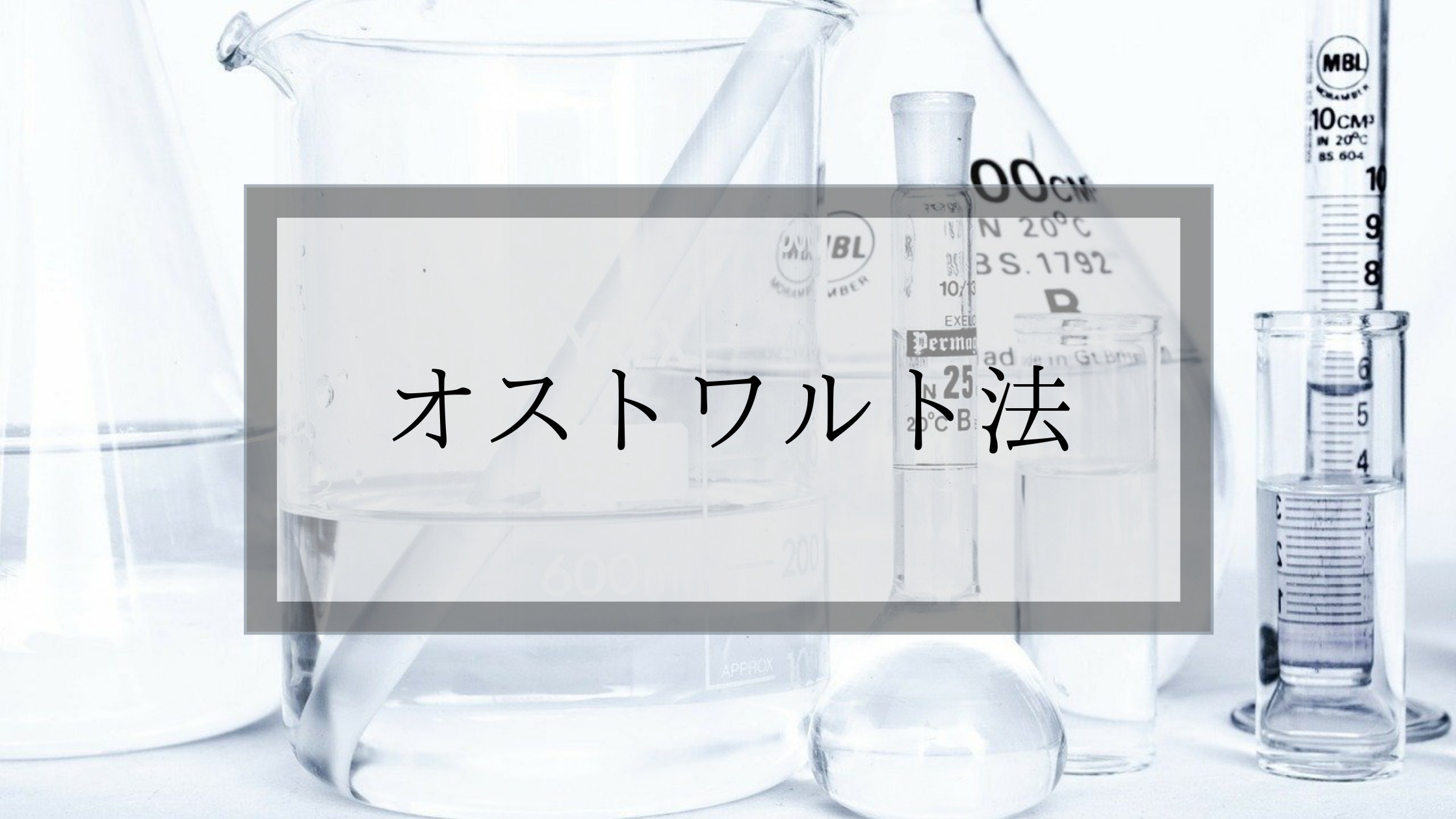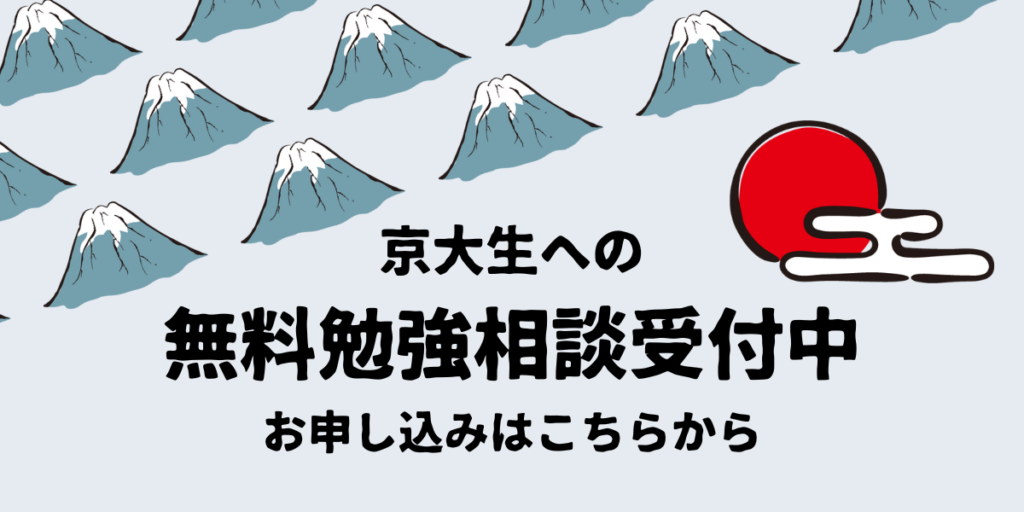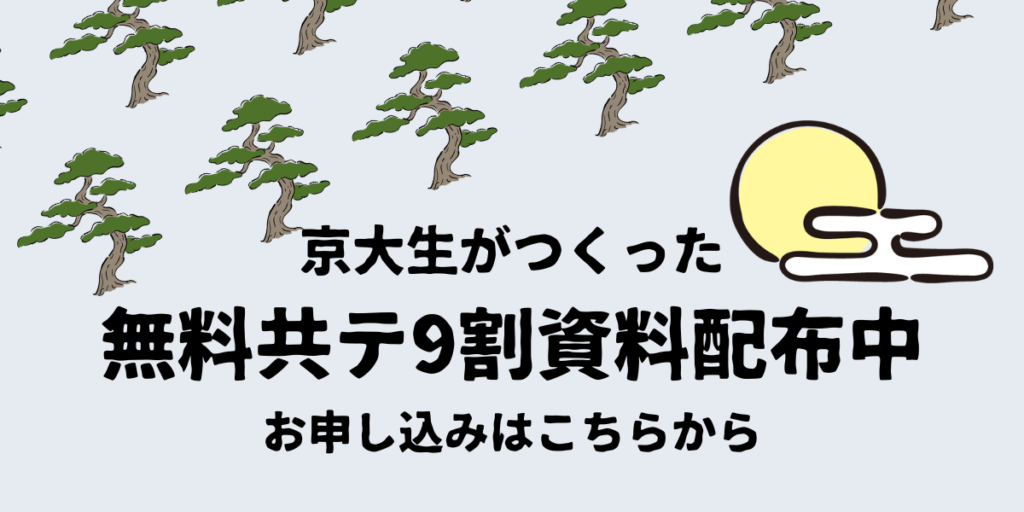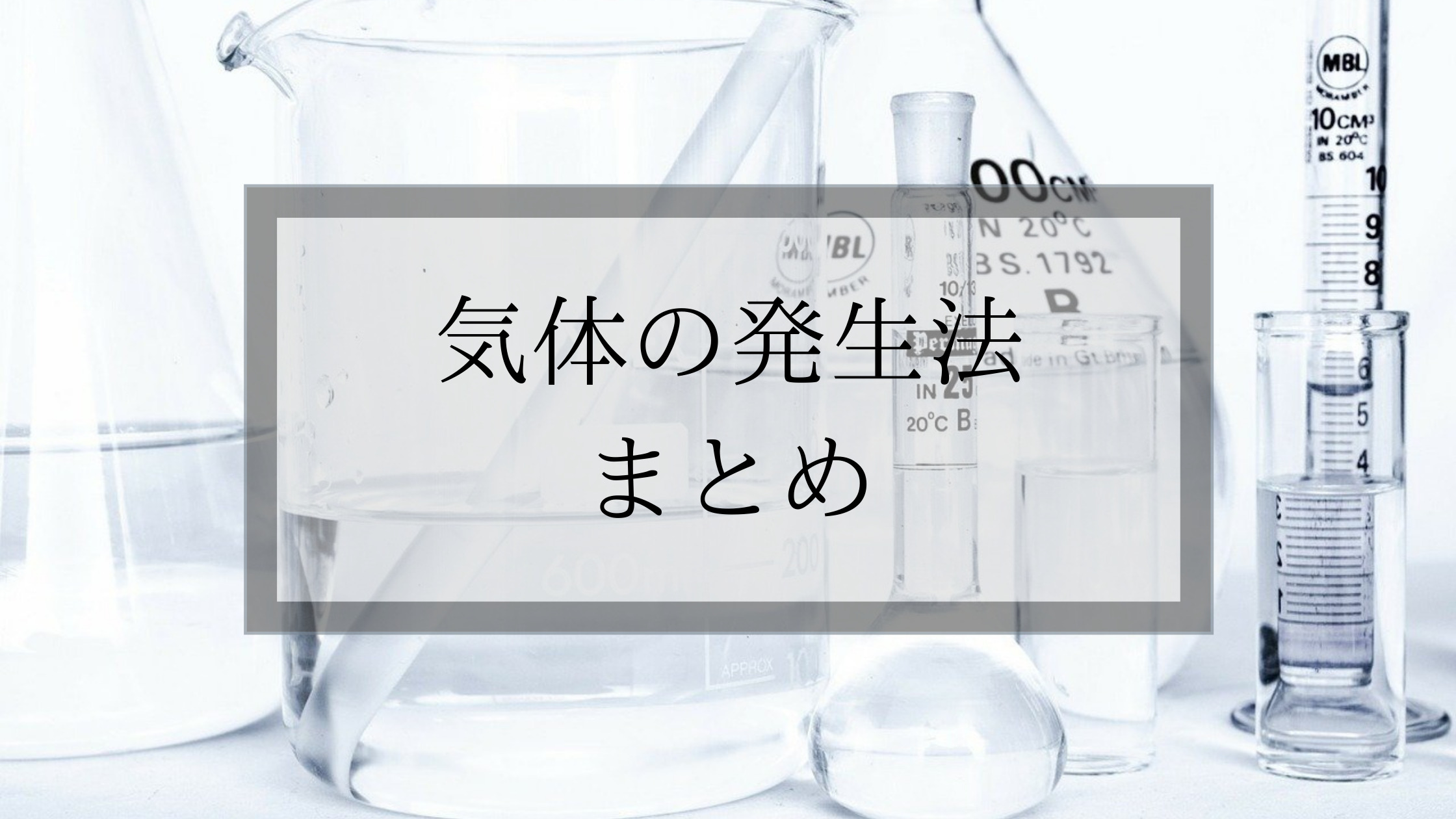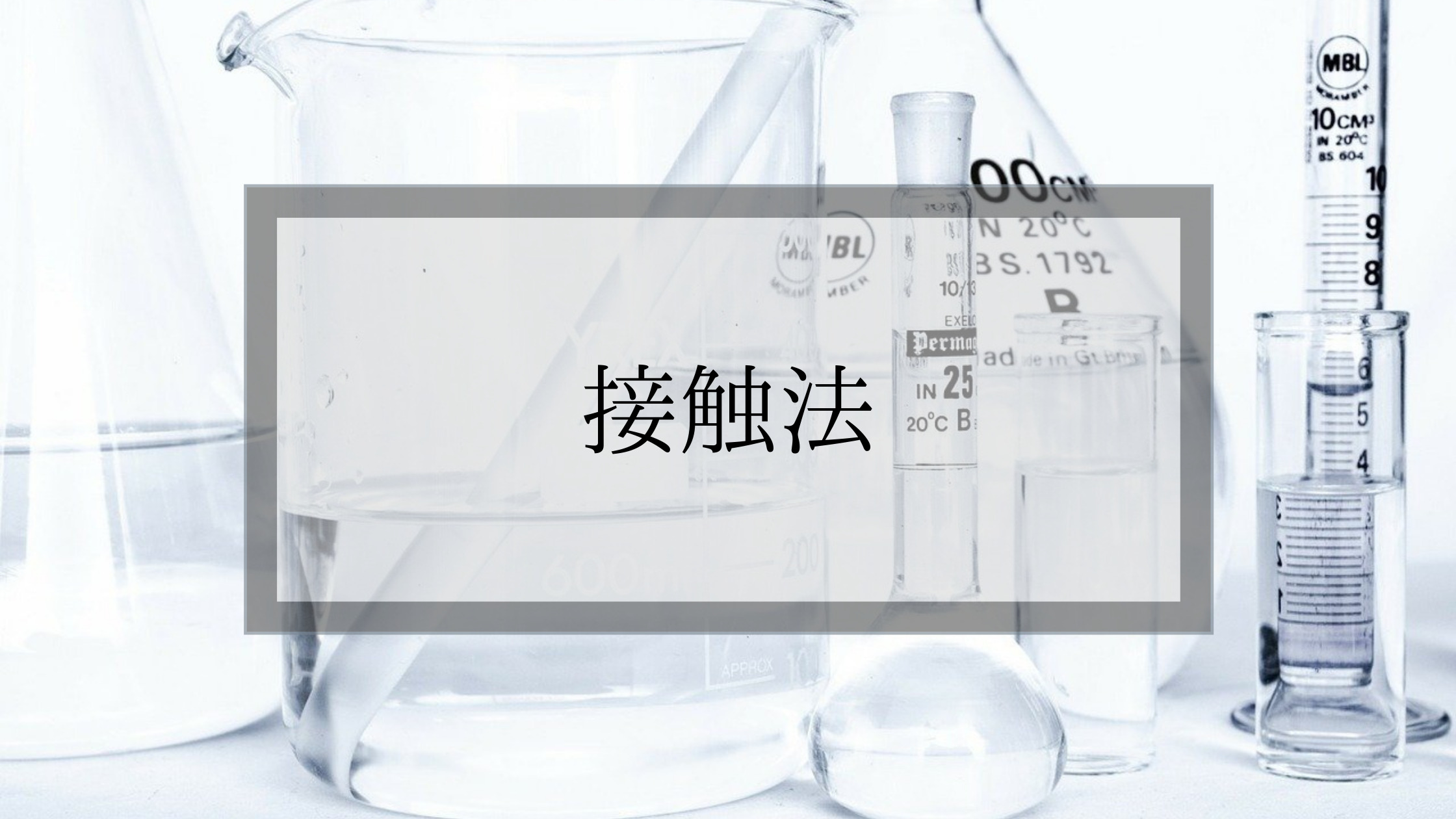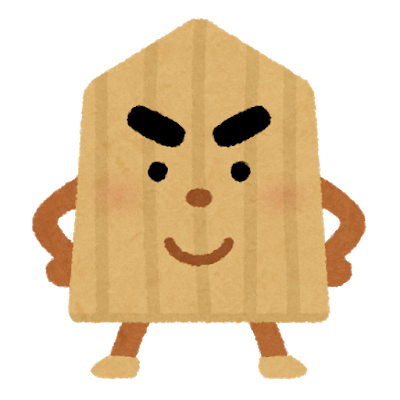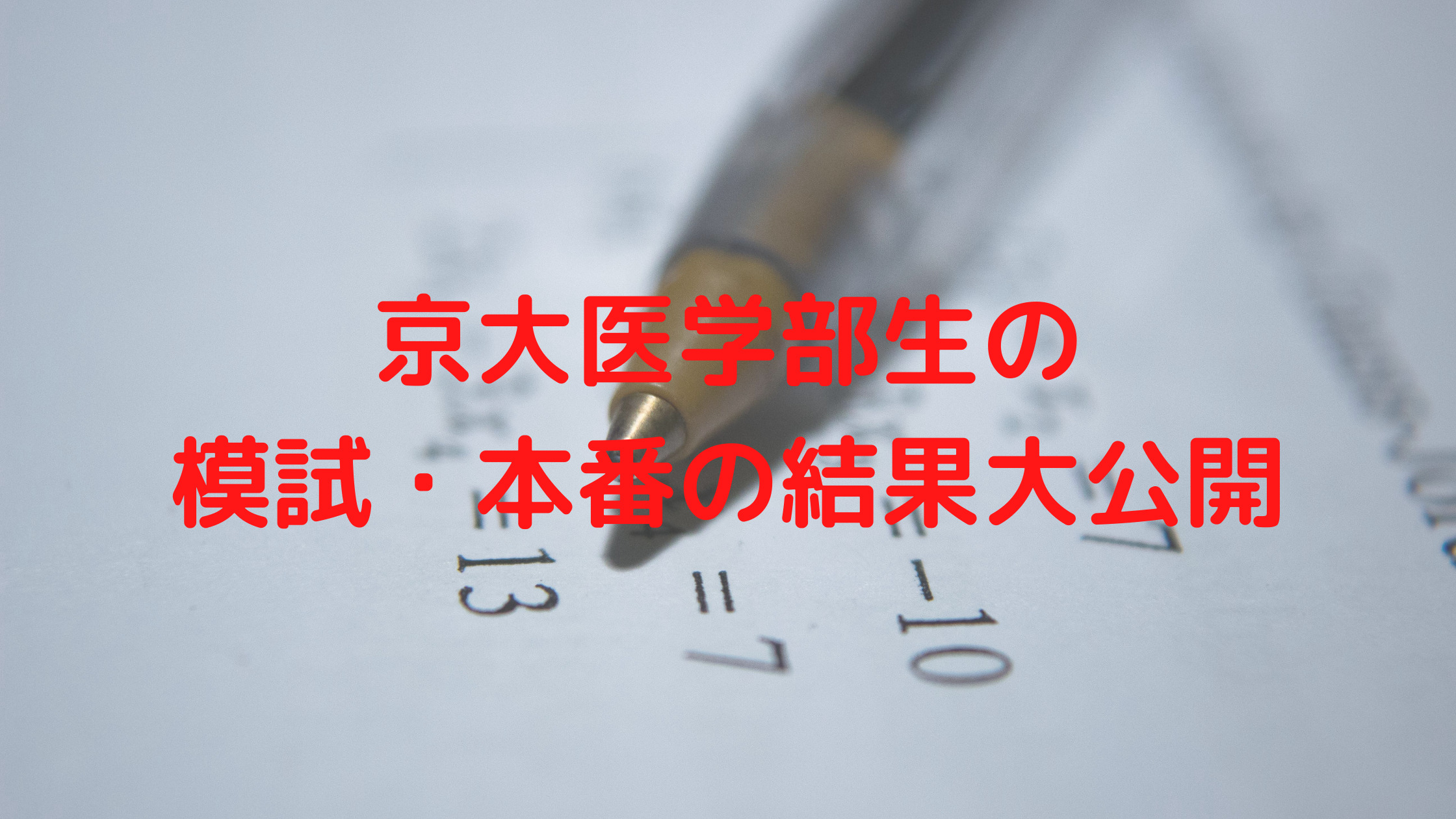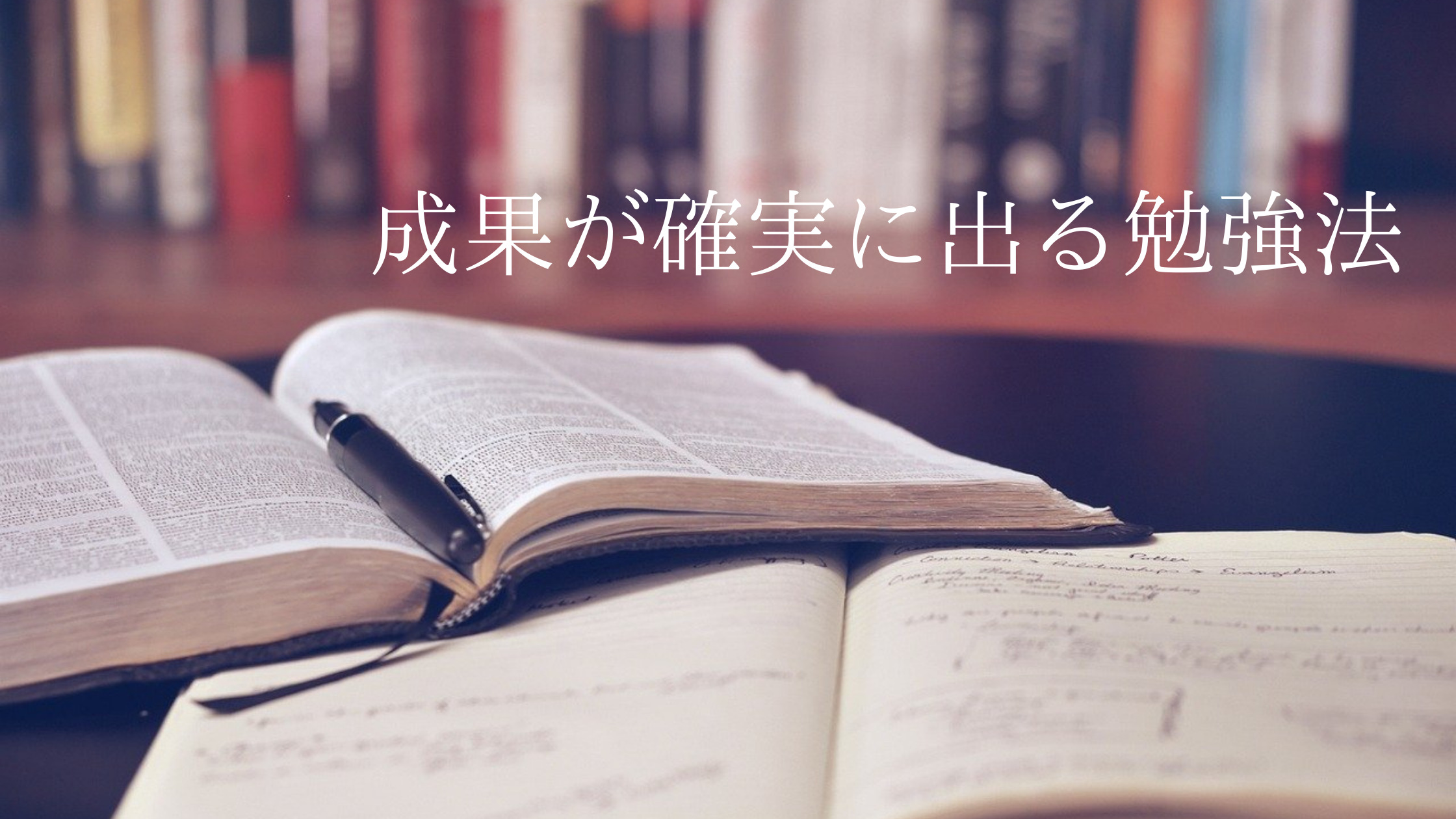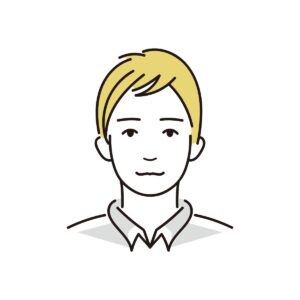
オストワルト法について詳しく知りたい
オストワルト法の反応式が書けない
今回はこのような悩みを解決します。
オストワルト法は接触法と並び、マーク試験で頻出です。今回の記事で知識を完璧なものにしてください。
プロフィール
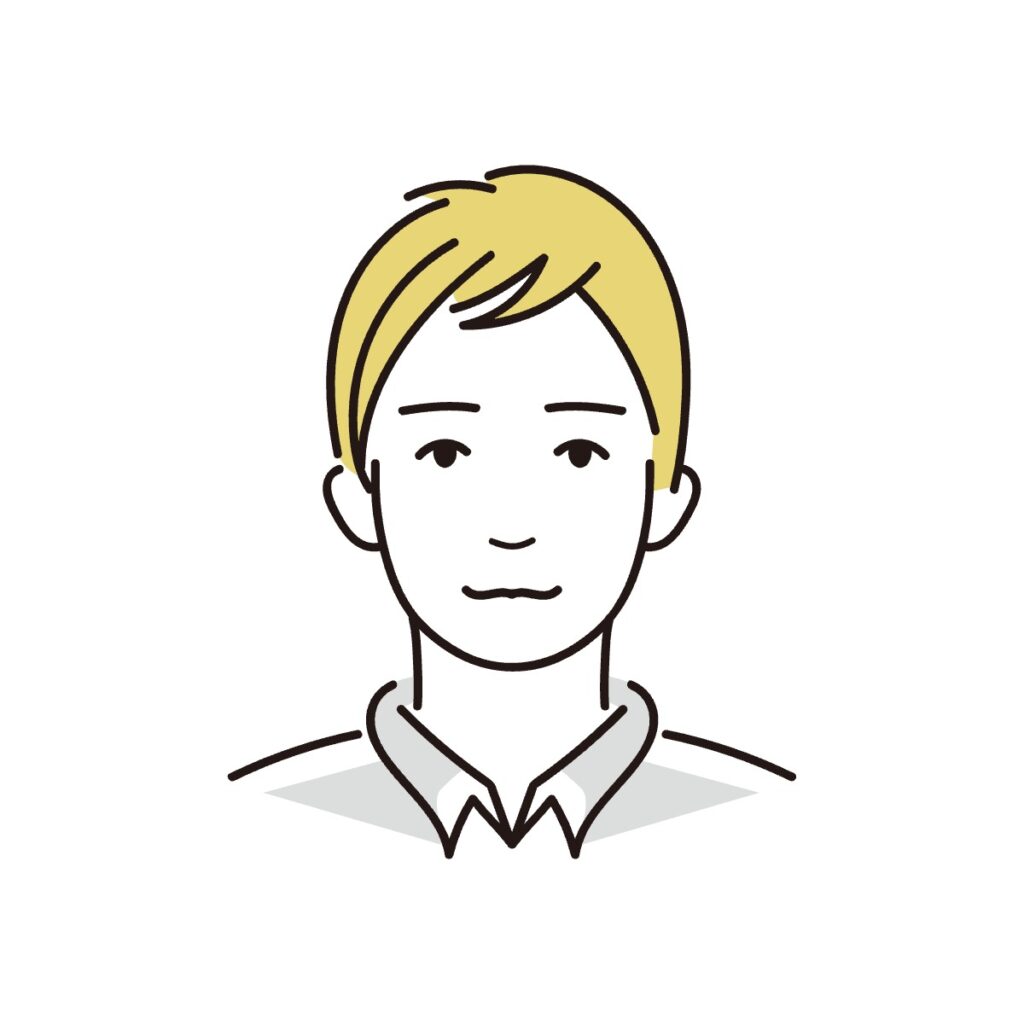
目次
オストワルト法とは硝酸の工業的製法である
まずオストワルト法とは何かを説明します。
オストワルト法とは、硝酸の工業的製法になります。
工業的製法とはどういうことかというと、「できるだけ安い費用でつくる方法」だと考えてもらえばよいと思います。
したがって、工業的製法というのはややこしい手順を踏むことが多く、オストワルト法も例外ではありません。
でも丁寧に説明していきますので、安心してついてきてください。
オストワルト法の反応式
まずはオストワルト法の反応式を見てみましょう。
オストワルト法
1 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
2 2NO +O2 → 2NO2
3 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO
まずはアンモニアを酸化することで一酸化窒素を作り出します。
そして一酸化窒素をさらに酸化して二酸化窒素とし、水に通すことで硝酸が得られます。
なお、3つ目の式では硝酸の他に一酸化窒素も生成されますが、これは再び2番目の式で再利用されます。無駄のない反応になっていますね。
アンモニア、一酸化窒素、二酸化窒素の発生法についてはこちらで復習しておきましょう。
反応式を1つの式にまとめる方法
ここで、先ほどの3つの反応式を1つにまとめる方法をご紹介します。
やみくもにまとめようとすると沼にはまってしまうので、しっかりと手順を覚えておきましょう。
反応式のまとめ方
- NO2を消去する
- NOを消去する
全体としてはオストワルト法は硝酸を得る反応です。生成物にNOやNO2が含まれることはありません。
したがって、NO2とNOを消去することでうまく反応式がまとめられます。
1.NO2を消去する
まずはNO2を消去します。
オストワルト法
1 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
2 2NO +O2 → 2NO2
3 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO
NO2が含まれるのは2,3番目の式なので「2番目の式×3+3番目の式×2」をすることで次の式が得られます。
4NO + 3O2 + 2H2O → 4HNO3
2.NOを消去する
続いてNOを消去します。
先ほどの式に1番目の式を足してあげることで次の式が得られます。
NH3 + 2O2 → HNO3 + H2O
これがすべての式をまとめたものになります。
オストワルト法の触媒
オストワルト法では触媒が使われます。
接触法の触媒と混同しがちであるため、よくマーク試験で問われるので覚えておきましょう。
オストワルト法の触媒
オストワルト法では、次の反応で触媒として白金(Pt)が使われる。
1 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
ちなみに接触法で使われる触媒は酸化バナジウム(V2O5)です。
オストワルト法のよくある計算問題の解き方
では最後にオストワルト法の計算問題を解いてみましょう。
ポイントさえ押さえれば何も難しいことはありません。
問題
アンモニアが10molある。このアンモニアがすべて反応するとして、質量パーセント濃度63%の硝酸は何g作ることができるか。
まずはオストワルト法の反応全体をまとめた式を作ります。
NH3 + 2O2 → HNO3 + H2O
ここからわかることは、アンモニア1molから硝酸1molが得られるということです。
ポイント
オストワルト法では、アンモニア1molにつき硝酸が1mol得られる。
したがって、今回の問題では硝酸は10mol得られることになりますね。
そして硝酸の式量は63ですから、硝酸は63×10=630(g)生成することがわかります。
あとはこれを63%に薄めたらどうなるかを考えます。仮に63%の硝酸がx(g)できるとすると、xのうち63%がオストワルト法でつくられた硝酸になるので、
x×63/100=630
が成り立ちます。あとはこれを解くと、x=1000(g)と答えが出ますね。
まとめ
今回はオストワルト法について解説しました。
反応式・触媒・計算の3点が問題になるところなので、よく理解しておきましょう。
おすすめ記事