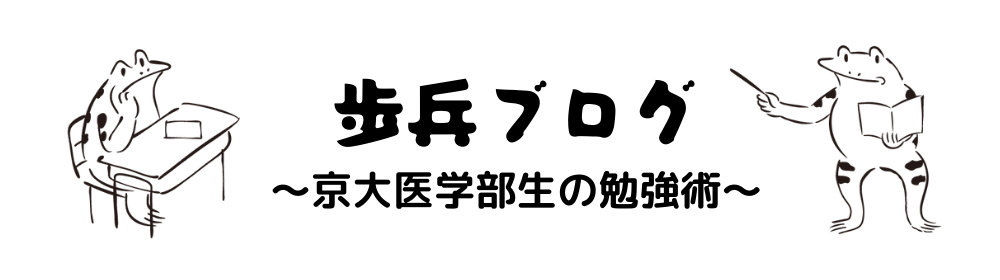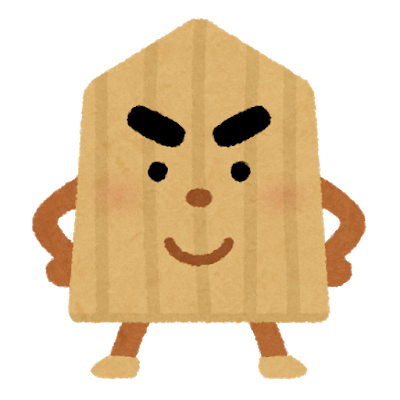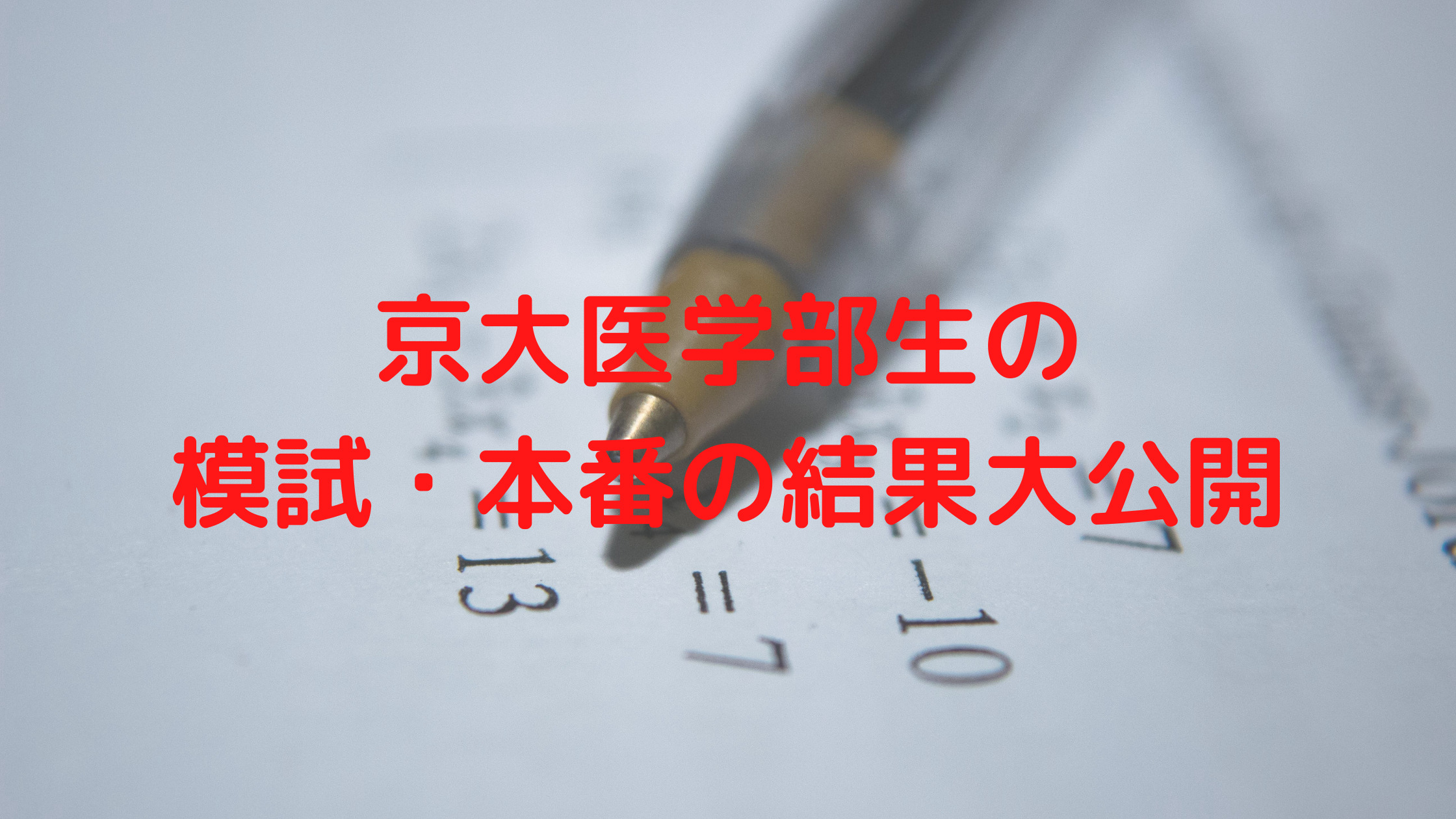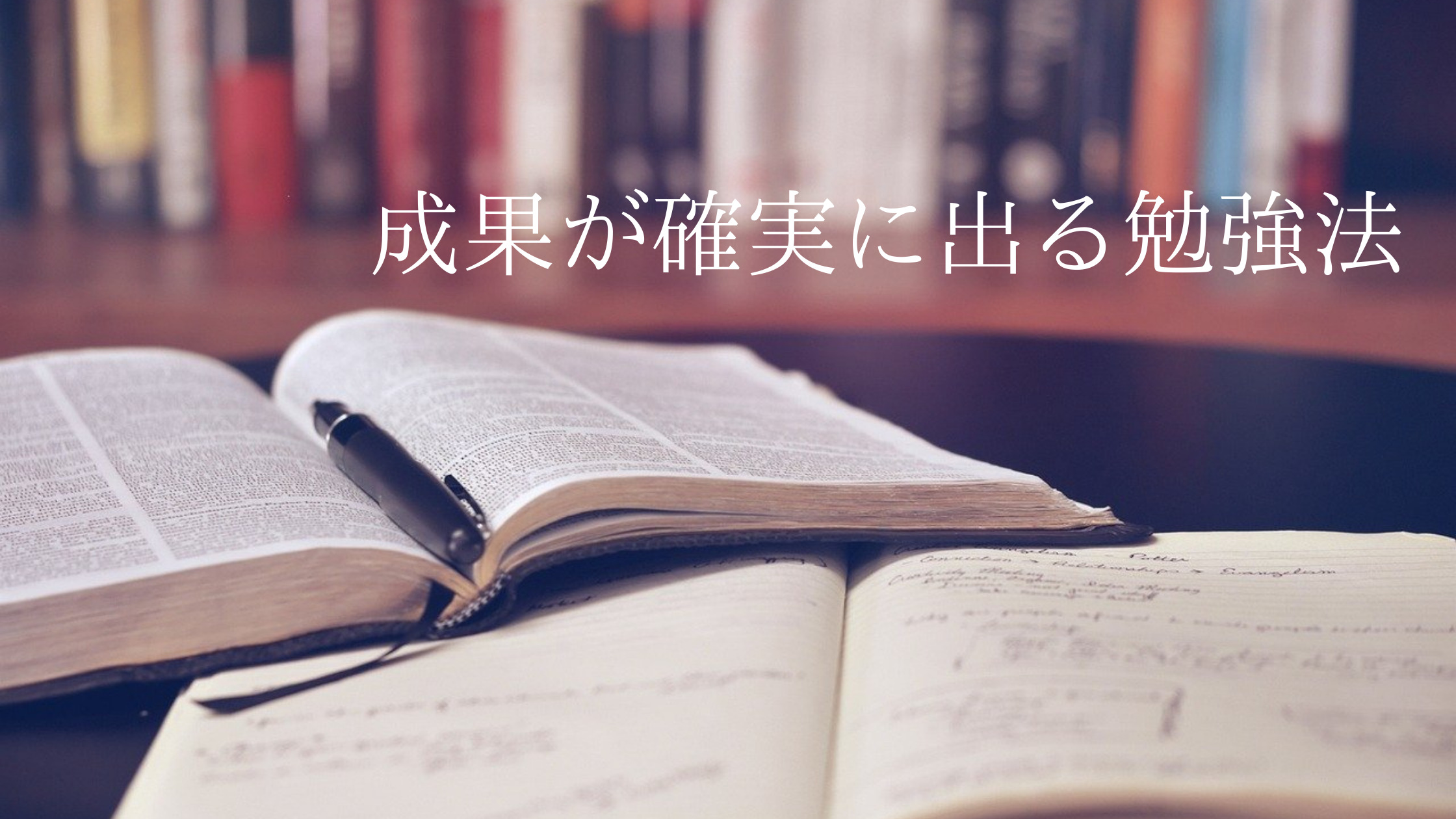「いくら勉強しても成績が上がらない」
「何をやればいいかわらないから、とりあえず問題集を1周してみた」
こんな人はいませんか。
もしかしたら、知らず知らずのうちに効率の悪い勉強をしてしまっているかもしれません。
ちゃんとインプットとアウトプットを区別して勉強できているでしょうか。これらを意識している人と意識していない人では同じ勉強時間でも得られるものに大きな差が出てしまいます。
逆に言えばインプットとアウトプットをうまく取り入れることができれば、今よりもはるかに成績の上がりやすい勉強ができるようになると言えます。
そこで今回はそもそもインプットとアウトプットとは何なのか、そしてそれらをどのように勉強に取り入れたらよいのかについて書いていきたいと思います。
それではいきましょう~。
目次
そもそもインプット・アウトプットって何
そもそもインプットとアウトプットという用語がわからない方もいると思うので、簡単に説明しておきます。
もともとはコンピューター用語ですが、今回はヒトについての意味にのみ着目します。
インプット…知識を取り入れること
インプットの具体例としては、授業を聞く、参考書を読むなどがあげられます。
アウトプット…取り入れた知識を取り出して活用すること
アウトプットの具体例としては、問題集の問題を解く、模試を受けるなどがあげられます。
インプットとアウトプットの意味については理解していただけたでしょうか。意味だけを知ると、
「どちらも当たり前でしょ。意識しないと何が問題なの」
と思われる方も多いと思います。そこで次に、それらを意識するべき理由について書いていきたいと思います。
インプットとアウトプットを意識するべき理由
一般的に人間は、このインプットとアウトプットを繰り返すことで何かを学習していきます。
したがって皆さんも普段、知らず知らずのうちにこれらを繰り返していることが多いです。
しかし人それぞれ、スムーズに成長できる分野とそうでない分野、つまり得意不得意がありますよね。なぜでしょうか。
それは、インプットとアウトプットのバランスを保つことが最も効率的な成長につながるからです。つまり、自分がうまくいっている分野では無意識のうちにインプットとアウトプットをバランスよく繰り返すことができているのです。
だからこそ、うまくいかない際はインプットとアウトプットを意識して2つのバランスをそろえてあげることが必要なのです。
2つのことを意識せず、どちらか一方に偏ったままの状態では、いくら努力したところでたいして成長できません。

もう少し理解していただくために、具体例にそって考えてみましょう。
あるゲームで強いモンスターをできるだけ早く倒したいとします。
ここでのインプットは攻略法を調べること。そしてアウトプットは実際にゲームをしてモンスターと戦うことです。
Aさんは、どうすればモンスターを倒せるのかを完璧に理解してからでないと戦っても意味がないと思っており、ひたすら攻略法の本やサイトをあさっています。では、攻略法を完全に理解したAさんは果たして今からゲームをして一発でモンスターを倒せるでしょうか。おそらく無理でしょう。
Bさんは実践あるのみだと考え、日々ゲームに明け暮れています。さあBさんはモンスターを倒せるでしょうか。もしかしたら倒せるかもしれませんが、それは何百回何千回とプレーして、必要な装備やアイテム、そして倒し方を自力で発見した後です。かなり時間がかかるでしょう。
Aさんはインプットに、Bさんはアウトプットに偏った例です。どちらも非常にもったいないですよね。インプットとアウトプットを意識できていないがために、モンスターを倒すために多くの無駄な時間を費やしてしまっています。
もちろん、両者とも時間をかければ目的は果たせるでしょう。たとえ時間がかかってもモンスターを倒せるならいいかもしれません。
しかし、勉強においてそんなことは言ってられません。受験本番までに合格するのに十分な力をつける必要があります。
勉強において効率よく成果を出すためには、やはりインプットとアウトプットを意識してバランスよく取り入れる必要があるのです。
インプットとアウトプットを取り入れた勉強法
インプットとアウトプットとは何を指し、それらをなぜ意識する必要があるのかについては理解していただけたと思います。
しかし、いきなり2つのバランスを意識して勉強をしろと言われても具体的にどうすればよいかわからないと思います。そこでこの章では、どうすればこれら2つを勉強に取り入れられるのかについて書いていきたいと思います。
まずは勉強におけるインプットとアウトプットについてそれぞれ確認しておきましょう。
インプット 授業を受ける・参考書を見る・問題の解説を読む
アウトプット 問題を解く、模試を受ける
ここまで読んでいただいた方は、やってはいけないことはすぐにわかるのではないでしょうか。それはインプットとアウトプットのどちらかに偏りすぎることでしたね。
やってはいけない勉強法
インプット偏向型 授業を受けて満足する・次々と新しい参考書を購入して読み漁る
アウトプット偏向型 問題を解きっぱなしにする・模試の復習をしない
インプット偏向型は、講師が有名で説明がわかりやすい場合や、購入した参考書が非常によくまとまっていると陥りやすいです。というのも、授業に出る、あるいは教科書を読むだけで分かった気になってしまうからです。このような人は長期休暇の講習を多くとる傾向もあります。
一方のアウトプット偏向型には「とにかくこの問題集を終わらせる」という意識で勉強していたり、もしの結果に過剰にこだわる人が当てはまります。このような人は中途半端にやった問題集や模試とその解説が机の周りにあふれかえるという特徴があります。

ではどのように勉強をしたらよいのでしょうか。答えはいたってシンプルです。
「問題を解く→間違いを確認して知識を補強→同じ問題を解く」のサイクルを繰り返すのです。
ここで大切なことは、同じ問題を繰り返すということです。なぜなら、間違ったところを正確にインプットできているかどうかは同じ問題を解くことでしか確認できないからです。
インプットした情報がすべて正確にアウトプットできてはじめてその問題を習得できたといえるのです。一つの問題を、もう何も出てこなくなるまでしゃぶり尽くしてください。
このように考えると、学校の小テストや課題というのは非常に理にかなっていると思います。というのもこれらは学校で習ったこと(インプットしたこと)についての問題を解といて知識の定着を確認する(アウトプットする)機会だからです。
本気で小テストと課題に取り組めば教科書レベルの内容はしっかりと定着するでしょう。ただ、「先生にやらされている」という義務感が生じるのでなかなか難しいですよね。実際に歩兵も怒られない程度にしかやっていませんでした。
その代わりと言っては何ですが、インプットとアウトプットのサイクルを意識した勉強は必ず自分で行いましょう。成果は確実に出るはずです。
まとめ
インプットとアウトプットについて、理解していただけたでしょうか。
最後に今回の内容をもう一度まとめておきます。
インプットとは知識を取り入れること、アウトプットとは取り入れた知識を取り出して活用することを指します。
歩兵がインプットとアウトプットを意識することが必要だと主張する理由は、効率的に学習するには2つのバランスが大切だからです。
「問題を解く→間違いを確認して知識を補強→同じ問題を解く」のサイクルを繰り返す。この方法を使えばインプットとアウトプットを両立することができます。
2とのことを意識するだけで、確実に勉強効率は上がります。今回得たことを生かして、周りに差をつけてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。質問等ありましたら、ぜひコメントをお願いします。
また、今回の内容が役に立ったと感じた方は、SNSでの拡散もお願いします。
ではまた!