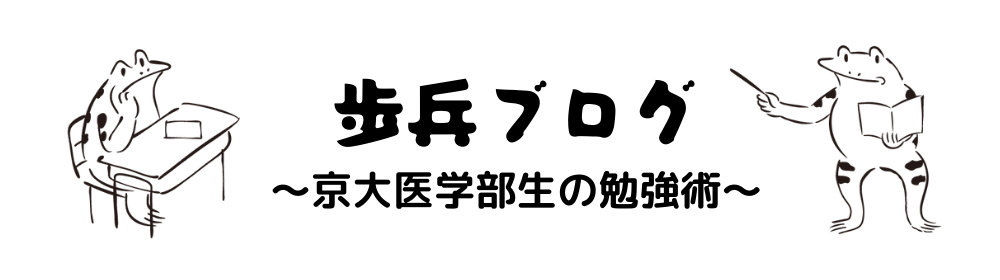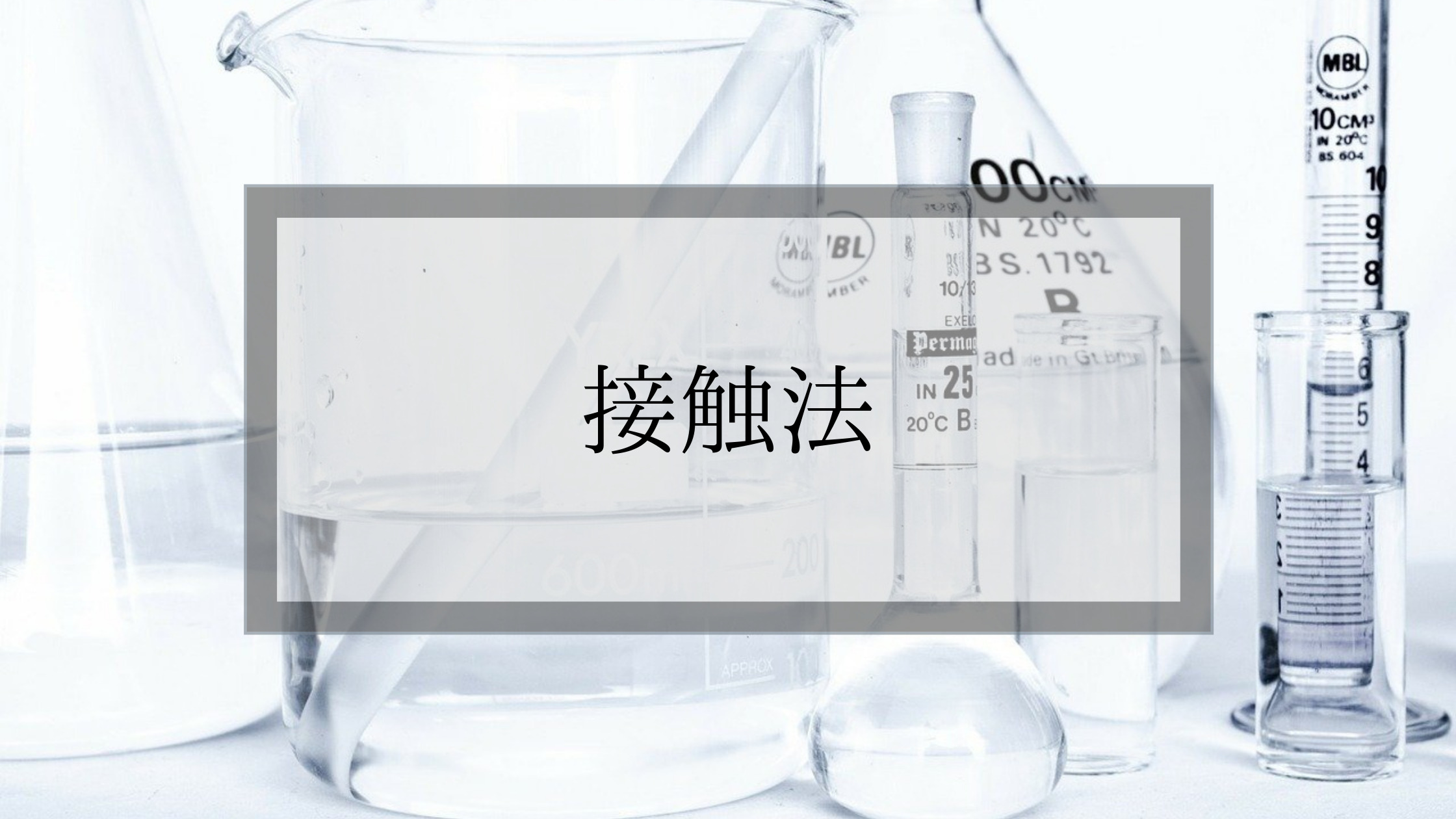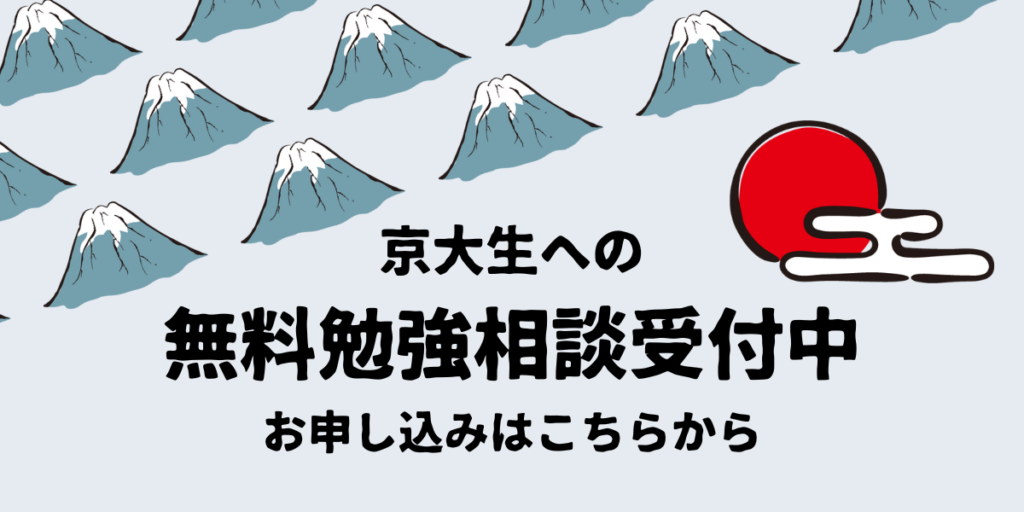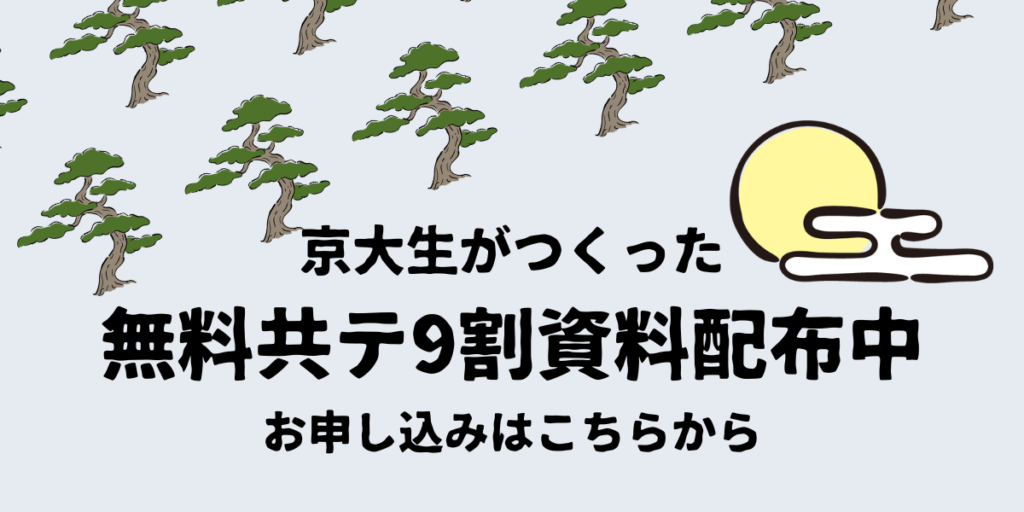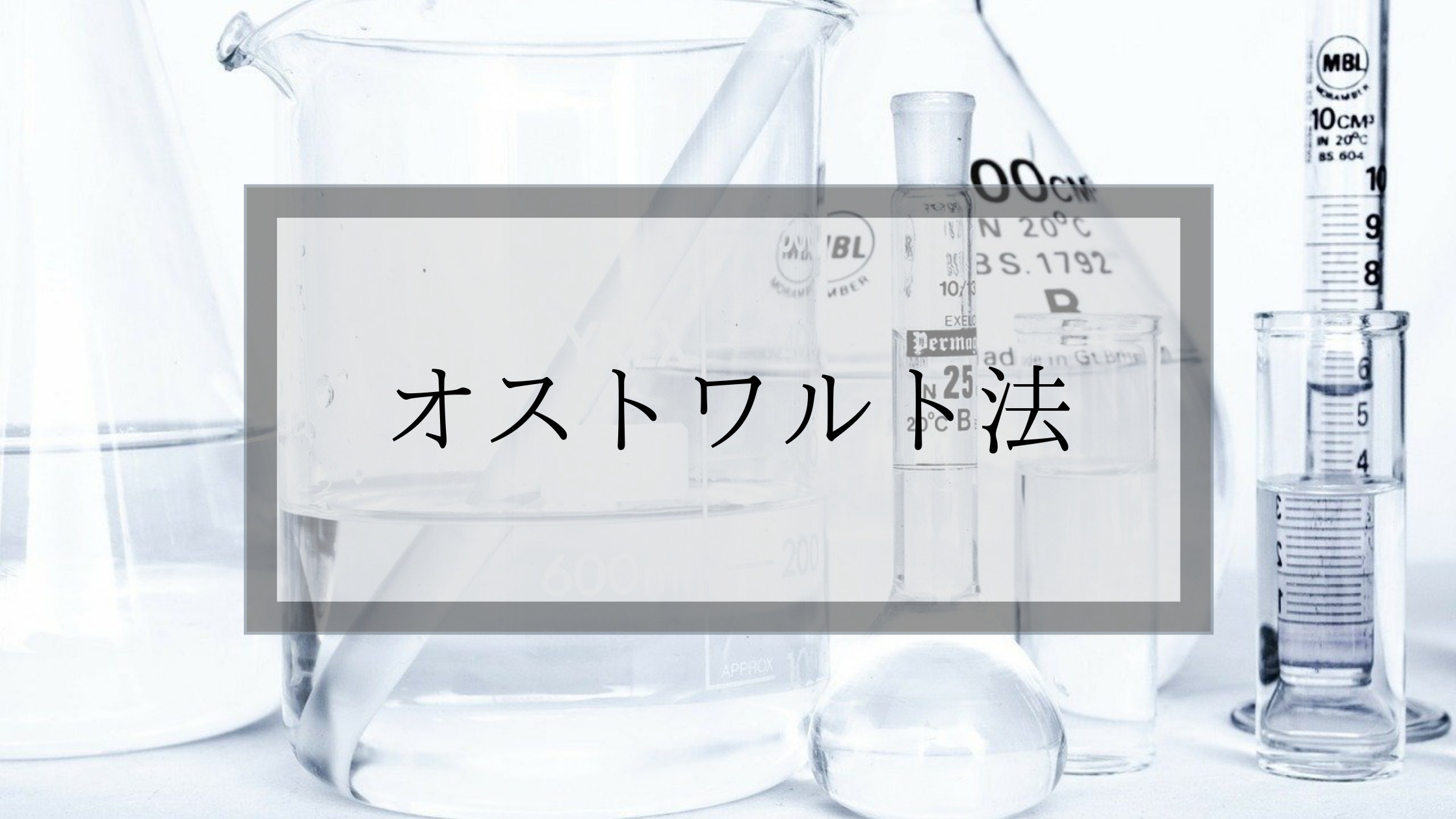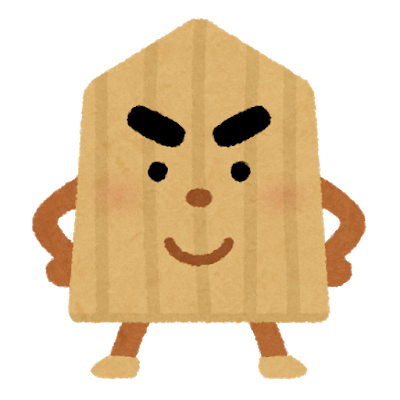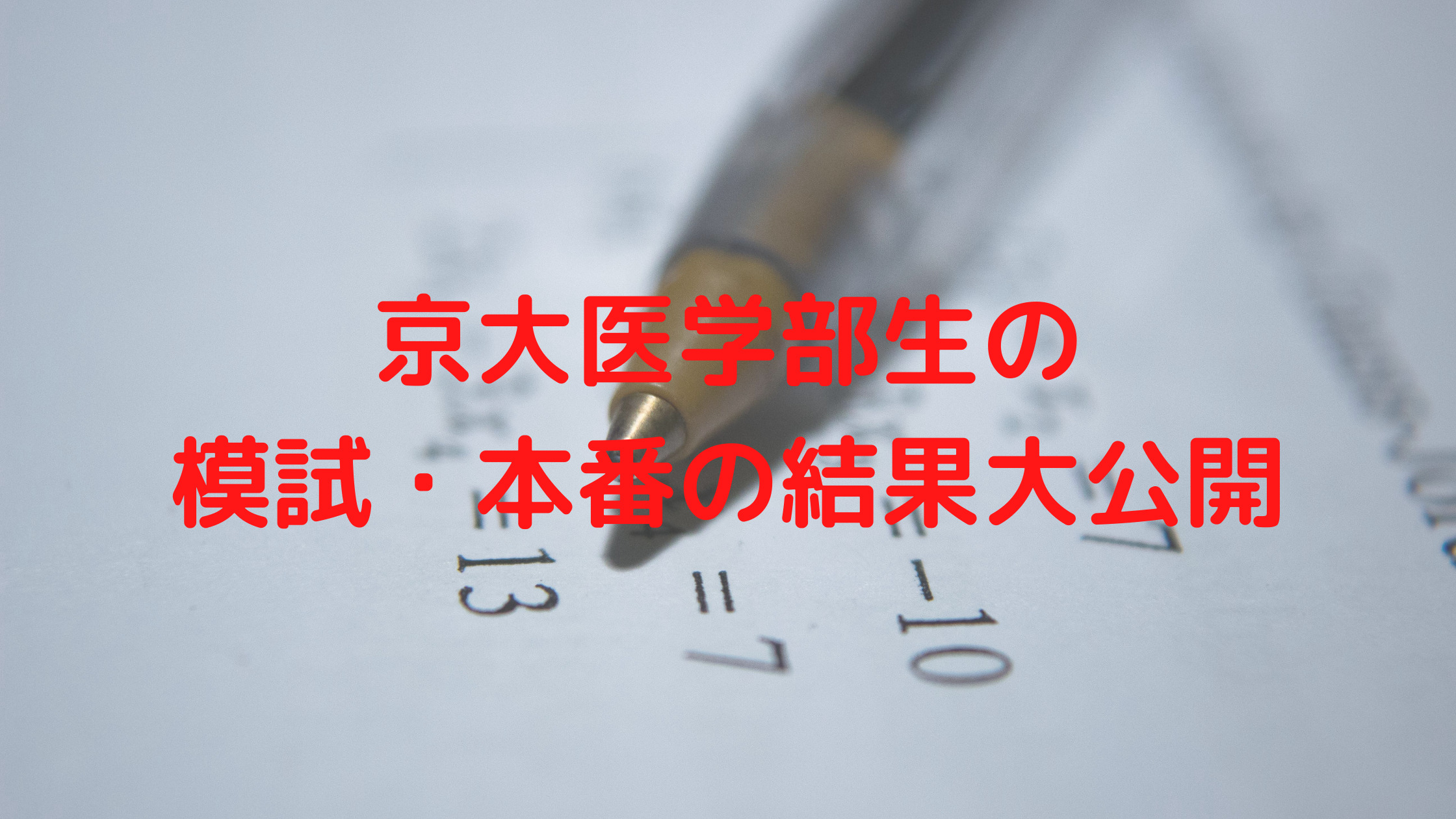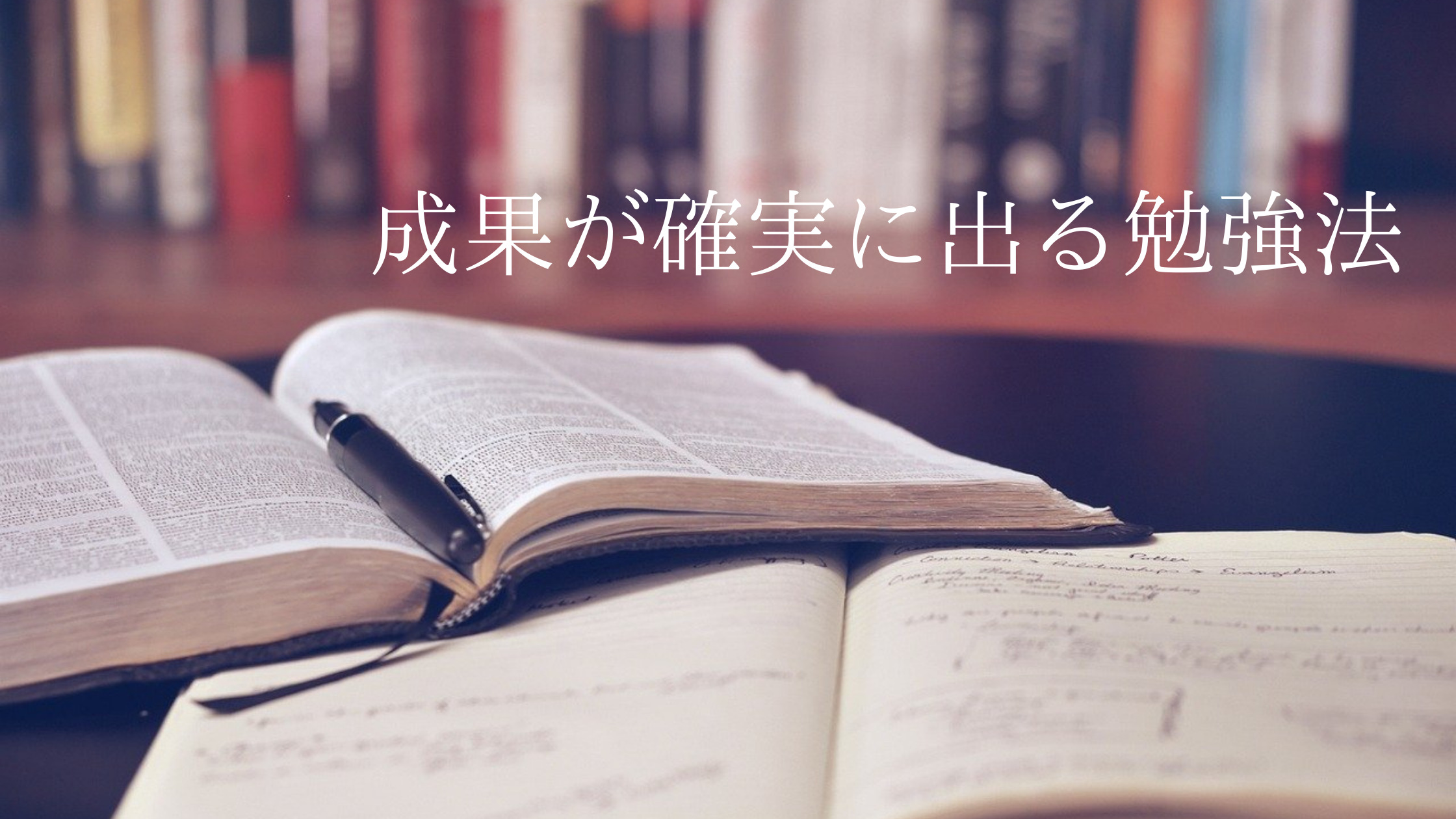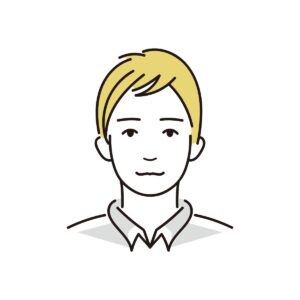
接触法の反応式や触媒についてよくわからない
今回はこのような悩みを解決します。
接触法はオストワルト法と並んで頻出。しっかりと知識を定着させておかないと痛い失点をしかねません。
今回の内容を参考に、接触法を完全理解してください。
プロフィール
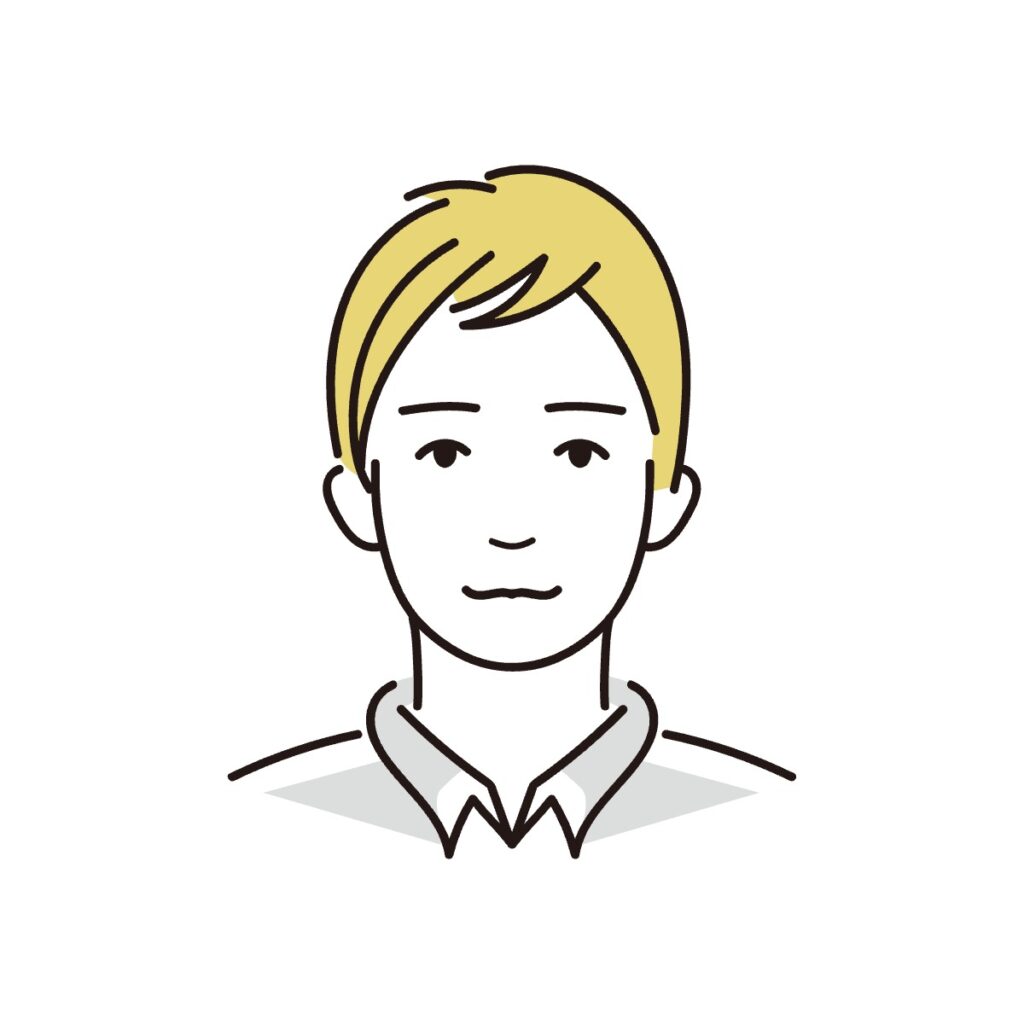
目次
接触法とは硫酸の工業的製法である
まず接触法とは何なのかを理解しましょう。
接触法とは、ずばり硫酸の工業的製法です。
工業的製法とは、「利益を得るための製法」と考えていただければOKです。
ではどのように硫酸を作るのかを学習していきましょう。
接触法の反応式
早速ですが、接触法の反応式を見てみましょう。
接触法の反応式
- S + O2 → SO2
- 2SO2 + O2 → 2SO3
- SO3 + H2O → H2SO4
単体の硫黄からスタートし、2段階の酸化でSO3を作り出します。
そしてSO3を水に通すことで硫酸ができあがります。
反応式を1つにまとめる方法
では次に、接触法の反応式を1つにまとめてみましょう。
反応式のまとめ方は次の通りです。
接触法の反応式のまとめ方
- SO2を消去する
- SO3を消去する
接触法は単体のSから硫酸を得る反応です。生成物にSO2やSO3が含まれることはありません。
したがって、そのことを利用してSO2およびSO3を消去してしまえば自ずと1つの反応式が得られます。
1.SO2を消去する
まずはSO2を消去してみましょう。
「1番目の式×2+2番目の式」をした次の式が得られます。
2S + 3O2 → 2SO3
2.SO3を消去する
次に、SO3を消去します。
先ほどの式に3番目の式×3を足してあげると、次のようになります。
2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4
これが3本の式をまとめたものになります。
接触法の触媒
さて、接触法の反応は実は簡単には起こりません。触媒が必要になるんですね。
そしてその触媒が何なのかがよく試験で問われます。
接触法の反応式
- S + O2 → SO2 ←Fe2O3
- 2SO2 + O2 → 2SO3
- SO3 + H2O → H2SO4
接触法においては1番目の反応でFe2O3が触媒として必要になります。
オストワルト法では触媒として白金(Pt)が出てきたのですが、それと混同しやすいので注意してください。
【発展】発煙硫酸とは
接触法についてよく出る計算問題の解き方
では最後に、接触法に関する計算問題の解き方を見ていきましょう。
問題
硫黄の単体が3.2kgあるとする。接触法で98%の硫酸は何kg得られるか。
この問題を解く上で必要になるのが、先ほどの3つの式をまとめたものになります。
2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4
ここから、硫黄1molにつき硫酸が何mol生成されるのかがわかりますね。
ポイント
接触法では、硫黄1molにつき硫酸が1mol生成する。
このことから、硫黄は(3.2×103)÷32=100(mol)あるので硫酸も100(mol)できることになります。
したがって、硫酸がx(g)得られるとすると、そのうちの98%が硫黄から作られた硫酸になるので
x×98/100=98(g/mol)×100(mol)
これを解くとX=1.0×104となるので、これをkgに直して答えは10kgとなります。
まとめ
今回は接触法に解説しました。
反応式・触媒・計算の3つを攻略して、ぜひテストでも完答できるようにしてください。
おすすめ記事